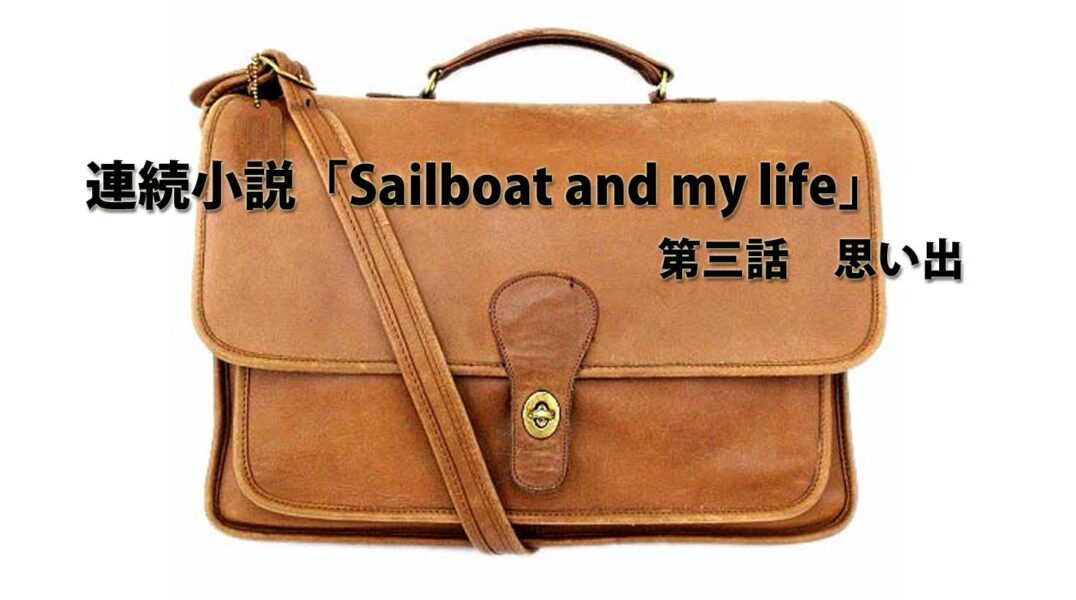古いコーチのバッグを見ると、つい昔のボスのことを思い出してしまう。今はかなりくたびれてしまったが、私がボスの家にお邪魔した時に頂いたバッグである。
私がボスから頂いた時はまだ新しく、しっかりとしていて艶もあった。ボスは私がまだ稼ぎも少ないことを理解していてくれて、ボスが使っていたものを与えてくれたのだった。
しかも使い古しなんかではなく、新品同様の物を事あるごとにプレゼントしてくれた。スーツやシャツにバッグに傘までも。そして娘さんの「おさがり」までも頂いたのだ。ほとんど傷みはなく、そのままお店に並べてもわからないくらい、程度の良いものばかりであった。
必ずシーズンごとに「フェデラルエクスプレス」で箱一つが送られてきた。差出人は奥様からであった。そして必ず家内宛に手紙が添えられてあった。
「今は暮らしが大変でも、必ず後数年でご主人は稼ぐようになれるから、頑張って支えてあげてね」何か困ったことがあったら必ず相談するようにと付け加えられていた。
箱を開けてみると娘の為のお下がりの洋服で、ほとんどラルフローレンのものだった。そんな訳でいつも私の娘がラルフローレンを着ているので、アパートの住人の中で噂になっていた。
ボストン周辺の子供でラルフローレンを着ている子供は、将来は必ずプレップスクールに通い、アイビーリーグや有名大学に進学することが決まっていたようなものだったからである。
ボスは私の直属の上司ではないが、私が新入社員の頃からとにかく目をかけてくれていたのだ。ランチにもよく誘ってくれて、不思議なことに待ち合わせ場所はフェンウェイパーク近くのマクドナルドであった。

呑みにもよく連れていってくれて、日本食レストランにも何度も連れて行ったくれた。フェンウェイパークではレッドソックスをよく応援したものだ。入場の始まる1時間前からボールパーク裏にあるバーでポップコーンとフレンチフライの大盛りを頼み、ボスはクアーズライト、私はバドライトで勢いをつけたものだ。
ボストンではバスケットはセルティックスがメジャーだった。ボスの友人にセルティックスのトレーナーがいて、たまにビルズバーに寄っては、マイケルジョーダンの攻略方などを話していた。
マサチューセッツ州は学問の街のイメージであるが、アメフトはペイトリオッツ、アイスホッケーはブルーインズが活躍していた。スポーツバーでは皆が画面を見ながら好きなことを語る。
ボスは、さも自分の意見が一番のように語る常連達に、熱くなるのはそのへんにして、そろそろレッドソックスを応援しようと呼びかけては、何度もチアーズを連発していた。そしてその声に連呼するのが私の仕事であった。

なんとなくビールの量が増えてきてザワつきはじめると、球場からアナウンスが聞こえてくる。そろそろ開場の時間であるが、すでに飲みすぎて酔っ払い、球場には入場できずにやけくそに大声で国歌を歌うものもいた。
フェンウェイでは平日の午後に、国歌を歌う練習している時もある。アメリカ人はどんな場所においても、どんな小さな地元の町内会レベルの大会でも、国旗を掲揚して国歌を歌うのである。
ボスの友人達がシーズンチケットを購入していて、私はその友人達が行けない時の代打で、いつもフェンウェイに無料で入場して、人一倍大きな声で国歌を歌ったものだ。
毎回無料なので、ボスの友人達には申し訳なく思いお金を払うと言っても、要らぬの一点張りで、お前が出世したらビップ席と美人の彼女を用意しろといつも言われた。
ボスの大学時代の友人達の合言葉は、”フェンウェイで乾杯” これが何を意味しているのかは、まったく理解できなかったが、私も一緒にチアーズを連呼していた。

とにかくボスとの思い出は数多くある。家族みんなでお世話になったケープコッド。長女は砂浜で興奮しすぎて遊びすぎ、その夜に熱を出してみんなを心配させたが、翌朝は誰よりも早く起きてまた海岸で遊んでいた。
私はほんの少しだけセーリングの知識があったため、ケープコッドの海岸付近をみんなを乗せて、JFKのような気持ちでセーリングをした。
夜になると地元のケープコッドリーグの野球の試合をみたり、シーフードをボスの友人が料理してくれて、ロブスターもたらふく食べた。

仕事においてはカナリ厳しい人であったが、とにかく可愛がってくれて面倒をみてもらった。そんな私がもっとも尊敬するボスがこの会社を去ろうとしている。私の人生を変えたボスであり人生の師でもある。家族共々いつも世話になっていた。
ボスは事業部のトップであり、ディビジョンマネージャーでありディレクターでもあった。各ディビジョンマネージャーのなかでも断トツにセンスが良く誰もが憧れるボスであった。
とにかく群を抜いてオシャレであったし、全ての事において独特の「こだわり」をもっていた。服装から音楽、レストランのメニューや賭け事までにも独特のスタイルを持っていたし、ジャパニーズレストランにおいては、姿勢や出で立ち・振る舞い、箸の持ち方にまでうるさかった。
何から何までボスから学んだのだ。そのボスが今、私の前からいなくなろうとしている。
第四話に続く